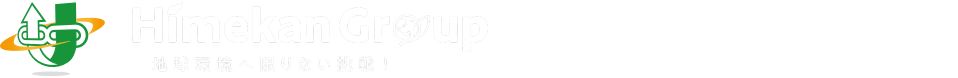変化に強い組織へ。
危機管理を日常に組み込む。
GOVERNANCE
危機管理の基本方針
自然災害・感染症・風評など、多様なリスクが企業を取り巻く中、
当社では「有事の際でも事業を止めない」ことを目指し、BCP(事業継続計画)策定と平時からの備えに取り組んでいます。
事業強靱化に向けて
- STEP 01
-
準備段階(事前設計)
バラバラだったリスクの捉え方を全社的に統一するための基盤づくり。
- 経営戦略室が中心となり、リスク管理ダッシュボードで管理すべき指標(KPI/KRI)を選定
- 各部門のリスク項目と評価指標をヒアリングし、指標の共通化を実施
- STEP 02
-
プロトタイプ作成(試験運用)
社内制度や会議運営、業務プロセスの透明化でガバナンスを「実行」に落とし込む。
組織横断的な内部統制体制を構築。- 一部の部署(例:営業部・収運部)で小規模な試験導入を実施
- 実際のデータ入力・収集の負担感を検証し、改善点を洗い出す
- STEP 03
-
全社展開(本格運用)
部門ごとの格差なく、リスク管理を“自分ごと”として定着させる。
- 全部署に向けて説明会・ワークショップを実施し、運用方法を周知
- 月1回の頻度でリスク管理レビューを行い、共有・点検をルーティン化
- マニュアルやQ&Aの整備により、どの部署でも扱える仕組みに
- STEP 04
-
PDCAサイクルの定着(継続改善)
管理体制を“形だけ”にせず、現場の声を活かして進化させる。
- 毎月「リスク管理委員会」を開催し、進捗確認と未達リスクのレビューを実施
- 各部門から改善提案を出し合い、仕組みそのものもアップデート
危機管理戦略達成に向けて
1 改善に向けた対策案
① 現場で機能するガバナンスづくり
実務・会議・役割における“しくみの土台化”
- 会議や検討の際に、「この議題の目的は何か」を明確化し、参加者と共有
- 経営理念や戦略を簡潔に示し、議論の軸に据える(=統制環境の整備)
- 議論前に「論点整理シート」などを用いて、議題の粒度をそろえる
- ファシリテーターが議論の枠組みや前提を随時確認し、会議の質を保つ
- 各会議やタスクにおいて「誰が責任を持つか」「誰が次のアクションを担うか」を明確に
- 必要に応じて、業務マニュアルも更新し、責任と権限を文書化
- 会議後に要点や課題、次の対応を簡潔に記録・共有
- 次回会議の冒頭で「前回からの進捗や改善状況」を振り返る仕組みを導入
② 体制構築と実行管理
部門連携・デジタル管理による「見える化と動かす仕組み」
-
経営戦略室が以下の役割を担い、管理体制のPDCAを推進:
- 危機管理方針の策定
- リスク評価と対応策の決定
- KPI/KRIの設定と進捗モニタリング
- 定期的なリスクマネジメント会議の開催
- 各業務プロセスを可視化して、リスクの発生しやすいポイントを特定。
- 各部門の役割・責任(職務分掌)を整理し、情報共有の仕組みや教育プログラムを整備。
③ 戦略連動と価値創出
経営レベルでの統合と「投資効果」につなげる視点
-
危機管理に以下の戦略テーマを連動させ、実効性を高める:
- 脱炭素経営戦略(環境リスクへの対応)
- 人的資本経営戦略(人材育成と組織力強化)
- 業務フロー・職務分掌に基づいた指標設計
- コスト削減を戦略の隠れたゴールとして意識。
- 各リスクに対して費用対効果を定量化し、予算へ反映。
- キャッシュフローや利益構造を部門ごとに理解する仕組みを整える。
2 KSF(成功要因)×KGI(業績目標達成)
取り組み事例
セキュリティアクション二つ星
中小企業が自ら情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。当社は二つ星を宣言し、情報管理体制の強化を通じて、お客様に安心してお取引いただける環境づくりに取り組んでいます。
ひめかんカレー
防災備蓄品として、公式キャラクター「ひめかんスマイリーくん」をパッケージにデザインされたカレーを作りました。保存期間は5年間で、温めなくても美味しいく食べられる長期保存食です。
成長サポート面談
従業員の日々の努力や成果を評価シートに記入し、所属部署長との面談を2か月に1回実施しています。相互理解を深め、成長の機会を提供することで、個人と会社のさらなる発展を目指しています。
もっと見る
DX推進
基幹システムをkintoneへ移行し、データを有効活用する基盤を整えています。また、営業活動の見える化にも取り組み、お客様にとって便利で満足度の高いサービスを実現するとともに、業務効率化も目指しています。
ISO14001 環境マネジメントシステム認証
2000年12月に国際規格ISO 14001認証を初めて取得して以来、継続的に認証を更新しています。最新の更新審査においても、厳格に設定した環境目標の達成状況を適切に報告し、環境事業へ貢献しています。
振動工具特別教育
安全衛生教育の一環として、厚生労働省通達「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について」(昭和58年5月20日 基発第258号)に基づき、事業者に求められている「特別教育に準じた振動障害防止のための教育」を、対象者が受講しました。
総合防災訓練
地震や火災などの災害発生時における初動対応力の向上と従業員の安全確保を目的に実施しています。避難・救助・消火に加え、災害時の対応手順を確認する机上訓練も行い、防災意識の定着を図っています。